 |
|
|
僥儗價僪僋僞乕偺斣慻HP偱偼昦婥傪専嶕偡傞偲偦偺昦婥偵偮偄偰愱栧偺堛巘偵傛傞嵟怴帯椕側偳堛妛忣曬偑偛棗偄偨偩偗傑偡丅
|
|
| 仸崅揷孫偑弌墘偡傞曻憲夞偺忣曬傪偍撏偗偟偰偄傑偡丅枅廡偺忣曬偼丄乽僥儗價僪僋僞乕乿偺儂乕儉儁乕僕傪偛棗壓偝偄丅 | |
 |
|
|
僥儗價僪僋僞乕偺斣慻HP偱偼昦婥傪専嶕偡傞偲偦偺昦婥偵偮偄偰愱栧偺堛巘偵傛傞嵟怴帯椕側偳堛妛忣曬偑偛棗偄偨偩偗傑偡丅
|
|
| 仸崅揷孫偑弌墘偡傞曻憲夞偺忣曬傪偍撏偗偟偰偄傑偡丅枅廡偺忣曬偼丄乽僥儗價僪僋僞乕乿偺儂乕儉儁乕僕傪偛棗壓偝偄丅 | |
| 仭3寧29擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1715夞 乽埨慡側堛椕梡杻悓偱捝傒傪娚榓乿 | ||
| 乣偑傫醬捝帯椕乣 | ||
|
|
||
 偑傫偱朣偔側傞恖偑憹偊偰偄傞拞丄娚榓堛椕偑拲栚偝傟偰偄傑偡丅 慜夞偵堷偒懕偒丄梽愳僉儕僗僩嫵昦堾儂僗僺僗挿偺抮塱徆擵乮偄偗側偑傑偝備偒乯愭惗 偵乽娚榓堛椕偵傛傞醬捝帯椕乿偵偮偄偰偍榖傪偆偐偑偄傑偟偨丅 娚榓堛椕偼丄姵幰偝傫偑偦偺恖傜偟偄惗偒曽偑偱偒傞傛偆偵條乆側柺偐傜巟墖偟偰偄偔堛椕偱偡丅 偦偺拞偱傕捝傒傪庢傝彍偔偲偄偆偲偄偆偺偼戝偒側栚揑偺堦偮偱偡丅 偦偺捝傒偵墳偠偰丄捔捝嵻偺嫮偝偑寛傔傜傟丄掕婜揑偵巊梡偡傞帠偱捝傒偺柍偄惗妶傪憲傞帠偑偱偒傞偺偩偦偆偱偡丅 |
||
| 仭3寧22擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1714夞 乽嬯捝傪榓傜偘婓朷傪尒偄偩偡堛椕乿 | ||
| 乣娚榓堛椕偺峫偊曽乣 | ||
|
|
||
|
尰嵼俁恖偵侾恖偑偑傫偱朣偔側傞帪戙偱偡丅 偑傫偺枛婜偵敽偆捝傒傪庢傝彍偒丄恖娫傜偟偄惗妶傪曐偮偺偑娚榓堛椕偱偡丅 崱夞偼丄梽愳僉儕僗僩嫵昦堾儂僗僺僗挿偺抮塱徆擵乮偄偗側偑傑偝備偒乯愭惗偵乽娚榓堛椕偺峫偊曽乿偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 抮塱愭惗偼丄壐傗偐偱惤幚側懳墳偱偍榖偟偟偰壓偝偄傑偟偨丅 係侽擭傎偳慜偵僀僊儕僗偱巒傑偭偨儂僗僺僗塣摦偐傜峀傑偭偨娚榓堛椕偼擔杮偱傕崱惍旛偑媫懍偵峴傢傟偰偄傑偡丅 乽帯椕偟側偄乿偲偐乽柊傜偝傟偰偟傑偆乿偲偄偆傛偆側娚榓堛椕偵娭偡傞戝偒側岆夝傕斣慻偺拞偱夝偄偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅 扨側傞恎懱揑側捝傒偩偗偱偼側偔丄乽惛恄揑嬯捝乿乽幮夛揑嬯捝乿乽僗僺儕僠儏傾儖儁僀儞乿偙傟傜慡恖揑側嬯捝偵懳偟偰庢傝慻傫偱偄偔帠偑娚榓堛椕偺廳梫側億僀儞僩偲側傞偦偆偱偡丅 偑傫懳嶔婎杮朄偲偄偆朄棩偱偦偺廳梫惈偑鎼傢傟偰偄傞娚榓堛椕偵偮偄偰丄師夞傕偍榖傪巉偄傑偡丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂3寧22擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅
|
||
| 仭1寧18擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1705夞 乽偍庰偼偄偄偗偳 僞僶僐偼偩傔乿 | ||
| 乣歯岲昳偲弞娐婍昦乣 | ||
|
|
||
 僞僶僐丄偍庰丄僐乕僸乕傗偍拑側偳偺歯岲昳偼寣埑傗弞娐婍偺昦婥偵偳偺傛偆側塭嬁偑偁傞偺偱偟傚偆偐丠 偦偙偱崱夞偼丄崙棫弞娐婍昦僙儞僞乕崅寣埑恡憻撪壢晹挿偺壨栰梇暯乮偐傢偺備偆傊偄乯愭惗偵偍榖傪偆偐偑偄傑偟偨丅 壨栰愭惗偼丄杮摉偵壐傗偐偱桪偟偔岅傝偐偗偰壓偝偭偨偺偱巚傢偢暦偒擖偭偰偟傑偄傑偟偨丅 弞娐婍昦偺婋尟場巕偼丄旍枮丒崅寣埑丒崅僐儗僗僥儘乕儖丒崅寣摐偱偡丅偙傟傜偺儕僗僋偼偆傑偔僐儞僩儘乕儖偟偨偄偱偡偹丅 偝偰丄歯岲昳偑弞娐婍昦偵梌偊傞塭嬁偱偡偑丄僞僶僐傪媧偭偰偄傞恖偼媧偭偰偄側偄恖偵斾傋偰丄嫊寣惈怱憻昦傗怱嬝峓嵡偑俀乣俁攞丅 怱憻偺撍慠巰偵偄偨偭偰偼丄抝惈偼侾侽攞丄彈惈偼俆攞嬤偔偱偡丅偄偐偵怱憻偵埆偄偐偲偄偆偙偲偱偡偹丅 嬛墝偺岠壥偼侾乣俀擭偱昞傟傞偦偆偱偡偐傜丄堦崗傕憗偔嬛墝偟偰偄偨偩偒偨偄偱偡丅 傾儖僐乕儖偼丄峊偊栚側傜堸傫偩曽偑傛偄偦偆偱偡丅抝惈偼丄侾擔價乕儖侾杮傑偱丄彈惈偼儚僀儞侾攖傑偱偲偄偆偺偑偍偡偡傔偩偦偆偱偡丅 僐乕僸乕傗偍拑偼丄忢幆揑側斖埻偱侾擔悢攖堸傓暘偼慡偔栤戣偁傝傑偣傫丅 僐僐傾偲僠儑僐儗乕僩傕彮偟側傜寣娗偺摥偒傪椙偔偟偰偔傟傞偦偆偱偡丅 揔検傪庣偭偰歯岲昳傪妝偟傓偙偲偑戝愗偱偡偹丅偨偩偟丄僞僶僐偼埆偄塭嬁偟偐偁傝傑偣傫偐傜丄惀旕嬛墝側偝偭偰偔偩偝偄丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂1寧18擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭12寧28擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1702夞 乽偙傫側徢忬偑偁偭偨傜柪傢偢媬媫幵傪乿 | ||
| 乣嫻捝傪偒偨偡媬媫幘姵乣 |
||
|
|
||
 媫偵嫻偑寖偟偔捝偔側傞偲偄偆徢忬偑婲偙偭偨偲偒偵偼奆偝傫偼偳偆偝傟傑偡偐丠 崱夞偼乽嫻捝傪偒偨偡媬媫幘姵乿偵偮偄偰丄揤棟傛傠偢憡択強昦堾媬媫恌椕晹挿偺愹抦棦乮偄偢傒偪偝偲乯愭惗偵偍榖傪巉偄傑偟偨丅 愹愭惗偼丄僴僉僴僉偲揑妋側愢柧傪偟偰偔偩偝偄傑偟偨丅偪側傒偵愭惗偺僗僩儗僗夝徚偼栰媴娤愴偩偦偆偱偡丅 嫻偺捝傒傪偒偨偡昦婥偵偼嬞媫惈偑崅偄昦婥偑懡偔娷傑傟偰偄傑偡丅 拞偱傕媫惈怱嬝峓嵡丄嫹怱徢丄戝摦柆夝棧丄戝摦柆釒攋楐丄攛嵡愷徢側偳偼丄嬞媫惈偑旕忢偵崅偄昦婥偱偡丅 偦傟偧傟偺捝傒偺摿挜傕斣慻偺拞偱偍榖偄偨偩偄偰偄傑偡丅 栭拞偱傕媬媫幵傪屇傫偱丄偱偒傞偩偗憗偔昦堾傊偄偒傑偟傚偆丅 寛偟偰師偺梊栺傪懸偭偨傝丄帺暘偱塣揮偟偰峴偭偨傝偟側偟偱偔偩偝偄丅 昦堾偱偼丄徢忬偵壛偊偰慡恎偺恌嶡丄偝傑偞傑側専嵏傪偟偰恌抐傪妋掕偟丄帯椕傪偟傑偡丅 彮偟偱傕憗偔帯椕偑偱偒傟偽丄幮夛暅婣偺壜擻惈偑崅傑傞偲偄偆偙偲偱偡丅 峀偄斖埻偱捝傒偑婲偒偨傝丄旕忢偵嫮偄捝傒偑挿偔帩懕偡傞応崌偵偼偡偖偵媬媫幵傪屇傫偱偔偩偝偄丅 崱擔偍榖偟偺偁偭偨條側嬞媫惈偺崅偄昦婥偺曽偑巊梡偡傞媬媫幵偱偡丅僞僋僔乕戙傢傝偵巊偄丄偄偞偲偄偆帪偵媬媫幵偑懌傝側偄偲偄偆帠偑柍偄傛偆偵婥傪偮偗偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂12寧28擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭11寧23擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1697夞 乽怴偟偔岠壥揑側峈偑傫嵻偑搊応乿 | ||
| 乣斿擜婍壢偱偺暊峯嬀庤弍乣 |
||
|
|
||
 嵟嬤憹偊偰偄傞戝挵偑傫偱偼丄怴偟偄峈偑傫嵻偑巊傢傟偼偠傔丄帯椕惉愌偑旘桇揑偵椙偔側偭偰偄傞傫偩偦偆偱偡丅 嵟嬤憹偊偰偄傞戝挵偑傫偱偼丄怴偟偄峈偑傫嵻偑巊傢傟偼偠傔丄帯椕惉愌偑旘桇揑偵椙偔側偭偰偄傞傫偩偦偆偱偡丅崱夞偼丄戝嶃堛壢戝妛壔妛椕朄僙儞僞乕丒僙儞僞乕挿偺戨撪斾楥栫乮偨偒偆偪傂傠傗乯愭惗乽戝挵偑傫偺怴偟偄峈偑傫嵻傪巊偭偨壔妛椕朄乿偵偮偄偰偍榖傪偆偐偑偄傑偟偨丅 戧撪愭惗偼丄傢偐傝傗偡偄椺傪悘強偵偁偘偰丄怴偟偄峈偑傫嵻偵偮偄偰挌擩偵愢柧偟偰偔偩偝偄傑偟偨丅 戝挵偑傫偺峈偑傫嵻偼丄偙偺侾侽擭傪傒偰傕戝偒偔恑曕偟偨傛偆偱偡偑丄嵟傕怴偟偄乽暘巕昗揑帯椕栻乿偲偄偆峈偑傫嵻偼偑傫嵶朎偑憹偊偨傝揮堏偡傞帠傪捈愙慾巭偡傞傕偺偱丄戝曄岠壥揑偱偡丅 峈偑傫嵻偲偄偆偲怱攝側偺偑傗偼傝暃嶌梡偱偡偑丄嵟嬤偺戝挵偑傫偺壔妛椕朄偼奜棃偱峴偊傞傕偺傕懡偔丄暃嶌梡傪僐儞僩儘乕儖偟側偑傜丄僈儞偁傞偄偼帯椕偲忋庤偔晅偒崌偭偰偄偔偙偲偑壜擻偲側偭偰偒偨偲偄偆偙偲偱偡丅 偤傂丄栻暔椕朄偵惛捠偟偨愭惗偵偛憡択壓偝偄丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂11寧23擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭11寧16擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1696夞 乽庤弍偺彎偑彫偝偔夞暅偑憗偄乿 | ||
| 乣斿擜婍壢偱偺暊峯嬀庤弍乣 | ||
|
|
||
 暊峯嬀庤弍乿偲偄偆尵梩傪傛偔暦偔傛偆偵側傝傑偟偨丅晧扴偑彮側偔丄憗婜夞暅偑壜擻偩偲偄傢傟偰偄傑偡丅 崱夞偼丄娭惣堛壢戝妛嫵庼偺徏揷岞巙乮傑偮偩偨偩偟乯愭惗偵乽斿擜婍壢偵偍偗傞暊峯嬀庤弍乿偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 徏揷愭惗偼幚偵壐傗偐偱幚捈側報徾偺愭惗偱偡丅侾俋俋侽擭偵擔杮偺斿擜婍壢偱弶傔偰暊峯嬀庤弍傪偝傟偨偺偑徏揷愭惗偩偭偨偦偆偱偡丅 暊峯嬀庤弍偼庤弍偱偍暊傪戝偒偔愗傝奐偔戙傢傝偵丄暊暻偵彫偝側寠傪偁偗丄嬥懏惢偺摏傪憓擖偟丄偍暊偺拞偺憻婍傪娤嶡偟偨傝丄偦偺摏偐傜崅廃攇儊僗傗儗乕僓乕丄彫偝側僇儞僔側偳傪擖傟偰昦憙傪愗彍偟偨傝偟傑偡丅 斿擜婍壢偱傕偝傑偞傑側庤弍偵揔墳偝傟偰偄偰丄摿偵乽恡憻偑傫乿偺庤弍偵偼懡梡偝傟偰偄傞傛偆偱偡丅娭惣堛壢戝妛偱偼俀侽侽侾擭埲崀偢偄傇傫憹偊偰偄傞偺偩偦偆偱偡丅 幚嵺偺庤弍偺條巕偺幨恀傕尒偣偰偄偨偩偒傑偟偨偑丄儌僯僞乕夋柺偵庤弍偺條巕偑塮偟弌偝傟丄庤弍偵偐偐傢偭偰偄傞恖偡傋偰偑丄偦偺宱夁傪抦傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偡丅 暊峯嬀庤弍偼弍幰偺崅搙側媄弍偑昁梫偲偝傟傑偡偑丄崱偼巜摫幰偑偮偄偰尩偟偄僩儗乕僯儞僌偑峴傢傟偰偄偰丄媄弍偑偟偭偐傝偟偨偍堛幰條偑憹偊偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡偐傜丄埨怱偱偡偹丅 晧扴傕彮側偔夞暅偑憗偄偺偼偲偰傕婐偟偄偙偲偱偡偑丄昦婥偼憗偔傒偮偗傞偙偲偑堦斣偱偡偐傜丄掕婜恌抐傪庴偗傞偙偲偑戝愗偱偡丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂11寧16擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭10寧26擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1693夞 乽堛椕偺恑曕偵栶棫偪傑偡乿 | ||
| 乣帯尡偲椪彴尋媶乣 | ||
|
|
||
 怴偟偄栻傗帯椕朄傪奐敪偡傞帠傪栚揑偵幚巤偝傟傞偺偑丄帯尡偲椪彴尋媶偱偡丅 崱夞偼乽帯尡偲椪彴尋媶乿偵偮偄偰丄崙棫弞娐婍昦僙儞僞乕椪彴尋媶奐敪晹幒挿偺嶳杮惏巕乮傗傑傕偲偼傞偙乯愭惗偵偍榖偟傪偆偐偑偄傑偟偨丅 嶳杮愭惗偼丄憉傗偐偱慺揔側徫婄偺愭惗偱偡丅帟愗傟偺椙偄岅傝岥偱偍榖偟壓偝偄傑偟偨丅 椪彴尋媶偼恖娫傪尋媶懳徾偲偡傞堛椕尋媶偺帠偱堛椕偺恑曕偺楌巎傪怳傝曉傞偲椪彴尋媶偑戝偒側峷專傪偟偰偒偨偲偄偊傑偡丅 僕僃儞僫乕偺庬摋傗壺壀惵廎偺杻悓側偳偑桳柤偱偡偑丄崱偺帪戙偵晛捠偵庴偗傜傟傞帯椕傗専嵏偼偡傋偰夁嫀偵 峴傢傟偨偨偔偝傫偺椪彴尋媶偺惉壥偲尵偭偰傕偄偄偱偟傚偆丅 斣慻偺拞偱偼丄帯尡偲椪彴尋媶偺堘偄傕嫵偊偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅 椪彴尋媶偵偼丄偒偪傫偲偟偨尩偟偄儖乕儖偑愝偗傜傟偰偄傑偡丅 帺暘偨偪偺師偺悽戙偵偨傔丄偍堛幰條偺愢柧偵擺摼偱偒傟偽 愊嬌揑偵嶲壛偡傞偙偲傪峫偊偨偄偱偡偹丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂10寧26擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭10寧12擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1691夞 乽揑妋側帯椕偱擼峓嵡偺婋尟傪夞旔乿 | ||
| 乣撪栩摦柆嫹嶓徢乣 | ||
|
|
||
 偺偳偺椉懁傪捠偭偰擼偵寣塼傪憲偭偰偄傞戝愗側寣娗偑寊摦柆偱偡丅 崱夞偼丄崙棫弞娐婍昦僙儞僞乕擼恄宱奜壢堛挿偺斞尨峅擇乮偄偄偼傜偙偆偠乯愭惗偵乽撪寊摦柆嫹嶓徢偺嵟怴帯椕乿偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 斞尨愭惗偼擄偟偄尵梩傕傢偐傝傗偡偄昞尰偵抲偒姺偊偰壓偝傝丄忢偵榖傪儕乕僪偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅 嵟嬤丄怘惗妶偺墷暷壔側偳偵傛偭偰寊摦柆偑嫹偔側傞恖偑憹偊偰偄傞偦偆偱偡丅 偦偟偰偦偺傑傑曻抲偟偰偄傑偡偲擼峓嵡偵側傞壜擻惈偑偁傞偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅 帯椕偲偟偰偼栻暔椕朄丄奜壢揑帯椕丄偦偟偰僇僥乕僥儖傪梡偄偰峴偆寣娗撪帯椕偑偁傝傑偡丅帯椕偼偦傟偧傟偺姵幰偝傫偺慡恎偺忬懺側偳傪峫椂偟偰儀僗僩側傕偺偑慖戰偝傟傑偡偺偱専嵏傕戝偒側億僀儞僩偵側傝傑偡丅 傛傒偆傝僥儗價丂10寧12擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭9寧28擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1689夞 乽擼庮釃偺庤弍偑埨慡偱丄妋幚惈傪崅傔傞愭抂堛椕媄弍乿 | ||
| 乣夋憸巟墖僫價僎乕僔儑儞庤弍乣 | ||
|
|
||
 擼庮釃偼擼偵敪惗偡傞尨敪惈丄揮堏惈偺庮釃偱偡丅 崱夞偼丄戝嶃晎棫惉恖昦僙儞僞乕擼恄宱奜壢丒庡擟晹挿偺娵栰尦旻乮傑傞偺傕偲傂偙乯愭惗偵乽夋憸巟墖僫價僎乕僔儑儞庤弍乿偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 庤弍偺慜偵CT傗MRI嶣塭傪偟丄僨乕僞傪僫價僎乕僔儑儞僔僗僥儉偺僐儞僺儏乕僞偵庢傝崬傒嶰師尦僨乕僞傪嶌惉丅 億僀儞僞偺埵抲偑儕傾儖僞僀儉偵儌僯僞乕偺夋憸僨乕僞忋偵昞帵偝傟傑偡丅 夋憸巟墖僫價僎乕僔儑儞庤弍偼傑偝偵僇乕僫價傪巊偭偰僪儔僀僽傪偡傞傛偆側傕偺偩偦偆偱偡丅 庤弍傪峴偭偰偄傞埵抲偑偄偮偱傕惓妋偵昞帵偝傟傞偺偱丄埨慡偱鉱枾側庤弍傪峴偆偙偲偑偱偒傑偡丅 偍榖偟傪巉偭偰丄偙偺條側崅搙側庤弍偑幚嵺偵峴傢傟偰偄傞偙偲偵戝曄嬃偒傑偟偨丅 傔偞傑偟偄恑曕傪懕偗傞堛椕媄弍丄偙傟偐傜傕偝傜偵崅傑傞帠偑婜懸偝傟偰偄傑偡丅 傛傒偆傝僥儗價丂9寧28擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭9寧14擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1687夞 乽暘妱嵶朎恌偺嵟彫尷庤弍偱亀憗婜僈儞亁偱偼巰朣棪侽亾乿 | ||
| 乣弍拞鋁暘妱嵶朎恌乣 | ||
|
|
||
 怘惗妶偺墷暷壔側偳偑尨場偱偡偄憻偑傫偺姵幰偝傫偑擭乆憹偊偰偄傞傫偩偦偆偱偡丅 偡偄憻偑傫偼愄偐傜帯椕偺擄偟偄昦婥偲尵傢傟偰偒傑偟偨偑嵟嬤偱偼怴偟偄帯椕朄偑峴傢傟丄惉壥傕弌偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅 崱夞偼丄戝嶃晎棫惉恖昦僙儞僞乕徚壔婍奜壢暃晹挿偺峕岥塸棙乮偊偖偪丂傂偱偲偟乯愭惗偵乽庤弍拞偺鋁暘妱嵶朎恌乿偵偮偄偰巉偄傑偟偨丅 偡偄憻偼嫑偺宍偵偨偲偊傜傟傞偙偲偑偁傝傑偡偑丄偦偺拞偱摢晹丒懱晹丒旜晹偺俁晹暘偵傢偗傜傟傑偡丅 偡偄憻慡懱偵擷朎偑偁偭偰偳偙偑杮摉偵乽偑傫乿偺晹暘側偺偐傢偐傜側偄応崌偵丄庤弍拞偵堦扷偡偄憻傪愗偭偨忋偱丄偡偄憻偺偦傟偧傟偺晹暘偺鋁娗偺拞偵僇僥乕僥儖傪憓擖偟丄偑傫嵶朎傪妋掕偟傑偡丅 丂乽偑傫乿偲恌抐偝傟偨晹暘偩偗傪愗彍偱偒傞偺偱丄偑傫嵶朎偺側偄晹暘偼巆偡偙偲偑偱偒傞偲偄偆偙偲偱偡丅偙偺丄暘妱嵶朎恌偲暪梡偟側偑傜峴偭偨庤弍偱偼丄弍屻偺惉愌傕椙偄偦偆偱偡丅 恎懱偵晧扴偺彮側偄怴偟偄帯椕朄傕恑傫偱偄傑偡偑丄傗偼傝憗婜敪尒偑戝偒側忦審偵側傝傑偡偺偱丄掕婜揑側専恌傪庴偗偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂9寧14擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭8寧10擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1683夞 乽摢傪愗傜偢偵帯椕偡傞乿 | ||
| 乣擼寣娗撪庤弍乣 | ||
|
|
||
|
懡偔偺恖偑滊傞壜擻惈偑偁傞偲偄傢傟傞擼懖拞丅
僈儞丒怱憻昦偲暲傫偱擔杮恖偺巰場偺僩僢僾俁偵擖偭偰偄傑偡丅  崱夞偼恄屗巗棫堛椕僙儞僞乕拞墰巗柉昦堾丂擼恄宱奜壢晹挿偺嶁堜怣岾乮偝偐偄偺傇備偒乯愭惗偵乽擼寣娗撪帯椕乿偵偮偄偰偍榖傪偆偐偑偄傑偡丅 僥儞億姶偑偁傝傛偳傒偺側偄嶁堜愭惗偺偍榖偟偼丄暦偔傕偺傪傂偒偮偗傞椡偑偁傝傑偟偨丅 擼懖拞偺帯椕偼埲慜偼摢偺崪傪奐偄偰寣娗傪捈愙庤弍偡傞曽朄偟偐偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄嵟嬤偱偼恎懱偺拞偺寣娗偵嵶偄娗乮僇僥乕僥儖乯傪捠偟偰帯椕偡傞擼寣娗撪帯椕偑彊乆偵憹偊偰偒偰偄傞傫偩偦偆偱偡丅 寣娗撪帯椕偼恎懱偵懳偡傞塭嬁偑嵟彫尷偱偡傒傑偡偟丄擖堾婜娫傕抁偔丄偡偖偵幮夛妶摦偑壜擻偱偡丅 傑偩怴偟偄帯椕朄側偺偱丄挿婜偺帯椕惉愌偑晄柧側偙偲傗偡傋偰偺徢椺偑僇僥乕僥儖偱帯偣側偄偙偲傕棟夝偟側偔偰偼偄偗傑偣傫偑丄戝曄枺椡揑側怴偟偄帯椕朄乽擼寣娗撪帯椕乿偼偙傟偐傜傑偡傑偡敪揥偡傞偙偲偑妋幚帇偝傟偰偄傑偡丅 婜懸偑帩偰傑偡偹丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂8寧10擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭7寧27擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1681夞 乽廫暘偵媥梴偺庢傟傞帺暘偵揔偟偨悋柊帪娫傪乿 | ||
| 乣幙偺椙偄悋柊傪乣 | ||
|
|
||
|
壗偐偲朲偟偄尰戙幮夛丄乽挬婲偒傞偺偑偮傜偄乿乽栭偼側偐側偐柊傟側偄乿側偳丄悋柊偺栤戣偱擸傫偱偄傜偭偟傖傞曽傕彮側偔側偄傛偆偱偡丅
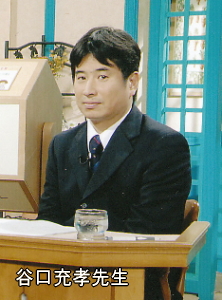 崱夞偼丄戝嶃夞惗昦堾悋柊堛椕僙儞僞乕晹挿偺扟岥廩岶乮偨偵偖偪丂傒偮偨偐乯愭惗偵乽幙偺椙偄悋柊乿偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 偖偭偡傝柊偭偨偲偄偆枮懌姶偲僗僢僉儕偟偨栚妎傔丒丒丒偦傫側幙偺椙偄悋柊偺偨傔偵偼懱撪帪寁傪挷愡偡傞帠偑戝愗側傫偩偦偆偱偡丅 傑偢丄婲彴帪崗傪堦掕偵偡傞偙偲偑昁梫偱偡丅柊傟側偔偰傕挬偼憗婲偒偡傞偙偲傪怱偑偗傑偟傚偆丅 傑偨丄椙偄悋柊傪偲傞偨傔偵偼丄拫娫偺惗妶偵傕拲堄偟傑偡丅 拫娫偼廫暘側岝傪梺傃妶摦揑偵惗妶偟偰儊儕僴儕傪偮偗丄怮傞慜偵偼儕儔僢僋僗偟偨帪娫傪偮偔傞帠偑戝愗側偳丄悋柊娐嫬夵慞偵偮偄偰傕嫵偊偰偄偨偩偄偰偄傑偡丅 惗妶傪夵慞偡傞偲嫟偵丄堦恖偱擸傑偢偵偍堛幰條傪庴恌偡傞偙偲傕偍偡偡傔偟傑偡丅 偍傠偦偐偵偟偑偪偱偡偑丄悋柊偼怱恎偺寬峃傪庣傞偨傔偺戝偒側梫場偱偡丅 悋柊傪戝愗偵偟偰丄惗偒惗偒偲偟偨枅擔傪憲傝偨偄傕偺偱偡丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂7寧27擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭7寧6擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1678夞 乽懱廘偼寬峃偺僶儘儊乕僞乕乿 | ||
| 乣偵偍偄偲寬峃乣 | ||
|
|
||
|
嵟嬤丄偵偍偄懳嶔僌僢僘傪椙偔尒偐偗傞傛偆偵側傝傑偟偨丅
擔杮恖偑帺暘傗懠恖偺偵偍偄偵晀姶偵側偭偰偒偰偄傞偲偄偆帠偱偟傚偆偐丠 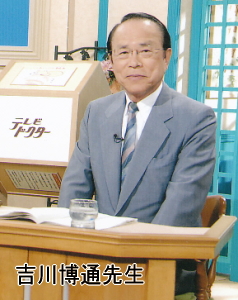 崱夞偼丄廧桭昦堾寬峃娗棟僙儞僞乕屭栤偺媑愳攷捠乮傛偟偐傢傂傠傒偪乯愭惗偵亀偵偍偄偲寬峃亁偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 崱夞偼丄廧桭昦堾寬峃娗棟僙儞僞乕屭栤偺媑愳攷捠乮傛偟偐傢傂傠傒偪乯愭惗偵亀偵偍偄偲寬峃亁偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅偄偮傕恎嬤側僥乕儅傪傢偐傝傗偡偔偍榖偟偄偨偩偔偺偱巚傢偢暦偒擖偭偰偟傑偄傑偡丅 帺暘偺懱廘傗岥廘傪婥偵偡傞恖偑憹偊偰偒偰偄傞偲尵偆偙偲偱偡偑丄乽偵偍偄乿偼応崌偵傛偭偰偼昦婥偲娭學偡傞応崌偑偁傞偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅 婥偵偟側偔偰傕椙偄傛偆側惗棟揑側偵偍偄偺応崌傕偁傞偺偱偡偑岥廘偺応崌偼丄帟廃昦傗拵帟丄歯岲昳偺偲傝偡偓丄挵撪娐嫬偺埆壔側偳尨場傕偝傑偞傑偱偡丅懱廘偺尨場傕摨條偵偄傠偄傠峫偊傜傟傑偡丅 巹偼丄懱挷偑埆偄帪偵愛庢偟偨怘傋暔偺偵偍偄偑堓偐傜捈愙奜偵弌偰偔傞偲巚偄崬傫偱偄傑偟偨偑丄偵偍偄偼寣塼偺拞偵庢傝崬傑傟偨暔幙偐傜敪惗偟偰偄偰丄偟偐傕懱拞傪弞娐偡傞傫偩偦偆偱偡丅 懱偐傜曻偭偰偄傞偝傑偞傑側偵偍偄偼寬峃偺僶儘儊乕僞乕偱偡偹丅 夁晀偵側傞昁梫偼偁傝傑偣傫偑丄偵偍偄偺梊杊懳嶔侾侽偐忦傕嫵偊偰偄偨偩偒傑偟偨丅 婥偵偟側偔偰傕椙偄偵偍偄側偺偐丄昦婥偵傛傞傕偺側偺偐敾抐偼擄偟偄偲偙傠偱偡丅揔愗側敾抐傪偡傞偨傔偵傕廃埻偺恖偲偵偍偄偵偮偄偰婥寉偵榖偣傞娐嫬傪嶌偭偰偍偒偨偄偱偡偹丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂7寧6擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭6寧29擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1677夞 乽旤偟偄帟暲傃偲丄岥尦偵側傝傑偡乿 | ||
| 乣妠曄宍徢偺庤弍乣 | ||
|
|
||
|
崱夞偼乽妠曄宍徢偺庤弍乿偵偮偄偰丄戝嶃戝妛戝妛堾帟妛尋媶壢嫵庼偺屆嫿姴旻乮偙偛偆傒偒傂偙乯愭惗偵偆偐偑偄傑偡丅 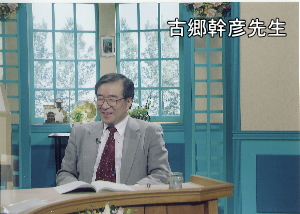 屆嫿愭惗偼恎怳傝庤怳傝傪傑偠偊偰撪梕偑椙偔揱傢傞傛偆偵偍榖偟偟偰壓偝偄傑偟偨丅 姎傒崌傢偣傪惓偟偔偡傞嫺惓帯椕偼傛偔抦傜傟偰偄傑偡偑丄嵟嬤偱偼帟暲傃偩偗偱側偔偁偛偺埵抲傪惓偟偔偡傞帯椕傗庤弍傪庴偗傞恖傕憹偊偰偄傞傫偩偦偆偱偡丅 妠曄宍徢偺徢忬偼丄怘帠偺帪偵傕偺傪姎傒嵱偒偵偔偔側偭偨傝丄敪壒偵忈奞偑弌偨傝丄妠娭愡徢偵側偭偨傝偲偄傠偄傠側偲偙傠偵塭嬁偡傞偲偄偆偙偲偱偡丅 椙偄岥尦偲偼丄忋偁偛偲壓偁偛偺僶儔儞僗偩偗偱側偔旤偟偄帟暲傃偑廳梫偱偡丅 偦偟偰摦偐偟偨崪偑屻栠傝傪偟側偄偨傔偵傕丄庤弍偼嫺惓帯椕偲堦懱偱峴偆昁梫偑偁傝傑偡丅偙偺帠偼愭惗偑孞傝曉偟偍偭偟傖偭偰偄傑偟偨傛丅 岥偺拞偱崪傪愗傞庤弍偲暦偄偰彮偟晐偔側傝傑偟偨偑丄愄偲斾傋傞偲庤弍偼傔偞傑偟偄恑曕傪偲偘偰偄偰埨慡偵側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅 偨偩丄悢擭娫偲偄偆挿偄帪娫偺偐偐傞帯椕偱偡偐傜丄傛偔愱栧偺偍堛幰條偲憡択偟偰帺暘偵崌偭偨椙偄帯椕寁夋傪棫偰偰帯椕傪庴偗偰偄偨偩偒偨偄巚偄傑偡丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂6寧29擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭6寧8擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1674夞 乽妠娭愡徢丂怺崗偵側傞昁梫側偟乿 | ||
| 乣偁偛偺擸傒傪壢妛偡傞乣 | ||
|
|
||
|
崱夞偼乽偁偛偺擸傒傪壢妛偡傞乿偲戣偟偰妠娭愡徢偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅偍榖偼丄戝嶃  戝妛戝妛堾帟妛尋媶壢嫵庼栴扟攷暥乮傗偨偵傂傠傆傒乯愭惗偱偡丅 戝妛戝妛堾帟妛尋媶壢嫵庼栴扟攷暥乮傗偨偵傂傠傆傒乯愭惗偱偡丅栴扟愭惗偺僜僼僩偱傢偐傝傗偡偄岅傝岥偵偼帺慠偲傂偒偮偗傜傟偰偟傑偄傑偡丅 忋偁偛偲壓偁偛傪偮側偖挶偮偑偄偺栶栚傪偟偰偄傞偁偛偺娭愡偱偡偑丄偦偺暋嶨偱惛岻側峔憿偵偼嬃偄偰偟傑偄傑偟偨両 妠娭愡徢偵側傞尨場偼堦奣偵摿掕偡傞帠偼偱偒側偄偦偆偱偡偑丄奜彎丄帟偓偟傝丄惉挿婜偺曃怘側偳偑偁偘傜傟傞偲偄偆偙偲偱偡丅偦偟偰丄傕偆侾偮丅僗僩儗僗側偳偵傛傞惛恄揑側尨場傕偁傞傫偩偦偆偱偡丅 尰戙幮夛側傜偱偼偱偡偑丄尭傜偟偨偄梫場偱偡偹丅妠娭愡徢偼偄傠偄傠側僞僀僾偑偁傝丄帯椕朄傕偝傑偞傑偩偦偆偱偡偑岥偑奐偗偵偔偄丄壒偑偡傞丄捝偄側偳偺徢忬偑弌偰偒偨帪偵偼鏢鏞柍偔愱栧偺偍堛幰條傪庴恌偟傑偟傚偆丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂6寧8擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭5寧25擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1671夞 乽摐擜昦恌椕偑曄傢傞乮係乯乿 | ||
| 傗偣偨恖傕拲堄偑昁梫乣崅楊幰偺偺摐擜昦乣 | ||
|
|
||
憹壛偵堦搑傪偨偳傞乽摐擜昦乿偼惗妶廗姷昦偺侾偮偲尵傢傟偰偄傑偡丅 摿偵崅楊幰偺姵幰偝傫偑懡偄偙偲偑栤戣偵側偭偰偄傞傛偆偱偡丅 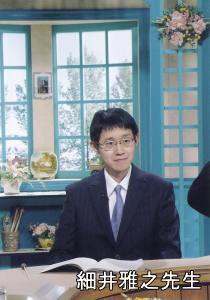 偦偙偱崱夞偼戝嶃巗棫憤崌堛椕僙儞僞乕戙幱撪暘斿撪壢晹挿偺嵶堜夒擵乮傎偦偄傑偝備偒乯愭惗偵亀崅楊幰偺摐擜昦亁偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 嵶堜愭惗偼杮摉偵桪偟偄娽嵎偟偱乽偍擭婑傝偺姵幰偝傫偺榖傪椙偔暦偄偰丄怱偺柺偐傜傕働傾偡傋偒乿偲偍偭偟傖偭偰偄傑偟偨丅 崅楊偵側傞偲嫟偵僀儞僗儕儞偺掞峈惈傗暘斿偺忬懺偑埆偔側傞偺偱丄摐擜昦偵側傝傗偡偄傫偩偦偆偱偡丅傑偨丄旍枮偼摐擜昦偵側傝傗偡偄偲偄偆僀儊乕僕偑偁傝傑偡偑丄憠偣偰偄傞恖偱傕崅楊幰偼儕僗僋偑崅偔丄廫暘側拲堄偑昁梫偱偡丅 偍栻傗帺屓拲幩傪朰傟傞姵幰偝傫傕懡偄偲偄偆偙偲偱偡偐傜丄廃傝偺曽傕婥傪偮偗偰偁偘偰壓偝偄偹丅 挿偄娫偺惗妶廗姷丄崌暪徢偺掱搙丄幮夛娐嫬偵偼屄恖嵎偑偁傝傑偡偐傜丄帯椕朄偼堦恖堦恖偵崌偭偨僥乕儔乕儊乕僪帯椕偑戝愗偩偦偆偱偡丅帯椕偵偮偄偰偼庡帯堛偺愭惗偵傛偔憡択側偝偭偰偔偩偝偄丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂5寧25擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭5寧18擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1671夞 乽摐擜昦恌椕偑曄傢傞乮俁乯乿 | ||
| 擠怭壜擻擭楊偵側偭偨傜堦搙寣摐専嵏傪乣彈惈偺摐擜昦乣 | ||
|
|
||
帺妎徢忬偑尰傟傞傑偱婥偯偐側偄姵幰偝傫傕彮側偔側偄偲尵傢傟傞摐擜昦丅 堦岥偵乽摐擜昦乿偲偄偭偰傕丄嘥宆偲嘦宆丄巕嫙偲戝恖丄抝惈偲彈惈側偳偝傑偞傑側傛偆偱偡丅 崱夞偼丄戝嶃晎棫曣巕曐寬憤崌堛椕僙儞僞乕曣惈撪壢暃晹挿偺榓孖夒巕乮傢偖傝傑偝偙乯愭惗偵乽彈惈偺摐擜昦乿偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 姵幰偝傫偲擇恖嶰媟偱昦婥偵惓柺偐傜岦偒崌偆榓孖愭惗偼杮摉偵棅傟傞慺揔側曽偱偟偨傛丅  彈惈偺摐擜昦丄抝惈偲偺堦斣偺堘偄偼丄傗偼傝擠怭丒弌嶻偱偡丅擠怭拞偺偍曣偝傫偑摐擜昦偺応崌偼偍暊偺拞偺愒偪傖傫偵愭揤惈堎忢側偳偺埆塭嬁傪媦傏偡偙偲偑偁傞偦偆偱偡丅 偦偺妋棪傪尭傜偡偨傔偵擠怭慜偐傜尩奿側寣摐僐儞僩儘乕儖傪偟偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅 傑偨丄旍枮丄摐擜昦偺壠懓楌偺恖傗擜摐嫮梲惈偺恖偼擠怭壜擻擭楊偵側偭偨傜丄徻偟偄寣摐専嵏傪庴偗偰壓偝偄丅 愭惗偼乽摐擜昦彈惈傕廫暘擠怭丒弌嶻偼壜擻偱偡偐傜偁偒傜傔傞昁梫偼偁傝傑偣傫偑丄擠怭慜娗棟傪偟偰偐傜擠怭偟偰偄偨偩偒偨偄偱偡偹乿偲偍偭偟傖偭偰偄傑偟偨丅 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂5寧18擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||
| 仭4寧6擔乮擔乯曻憲梊掕丂戞1665夞 乽扨恎晪擟偺寬峃娗棟乿 | ||
|
|
||
崱夞偼丄廧桭昦堾寬峃娗棟僙儞僞乕屭栤偺媑愳攷捠乮傛偟偐傢傂傠傒偪乯愭惗偵亀扨恎晪擟偺寬峃娗棟亁偵偮偄偰偆偐偑偄傑偟偨丅 媑愳愭惗偺偍榖偟偼丄偄偮傕偺傛偆偵愢摼椡偑偁傝丄傢偐傝傗偡偄撪梕偱偟偨傛丅 丂 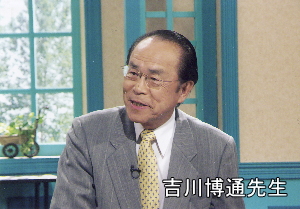 怴偟偄擭搙偵擖傞偲恖帠堎摦傗揮嬑側偳偱朲偟偔側傞僒儔儕乕儅儞偺曽偑懡偄偱偡偹丅 摿偵壠懓偲棧傟偰堦恖偱曢傜偡扨恎晪擟偼戝曄偱偡丅 堦斣婥偑偐傝側偺偼傗偼傝怘惗妶丅奜怘偽偐傝偱丄儊僞儃儕僢僋僔儞僪儘乕儉偵側偭偨傝懢偭偰暈偑擖傜側偔側偭偰偟傑偆偺偱偼丠偲怱攝偝傟傞墱條傕懡偄傛偆偱偡丅 偲偙傠偑丄嵟嬤偱偼戜強偵帺暘偱棫偭偰僶儔儞僗偺椙偄怘帠傪愛偭偰偄傜偭偟傖傞曽傕憹偊偰棃偰偄傞偦偆偱偡丅 椏棟傪妝偟傒側偑傜寬峃娗棟偑弌棃傞偺偱偡偐傜棟憐揑偱偡偹丅 偲偼尵偭偰傕偒傃偟偄僗僩儗僗偺偐偐傞扨恎晪擟幰偺寬峃娗棟丅 張悽弍幍儢忦傪嫵偊偰偄偨偩偒傑偟偨丅偦偺拞偱偱傕堦斣戝愗側偺偼怱棟柺丅 庯枴傗惗偒偑偄傪帩偭偰丄偳傫側帪偱傕慜岦偒偵暔帠傪峫偊傞偲偄偆偙偲偑惗妶偺巟偊偵側傞傛偆偱偡丅億僕僥傿僽僔儞僉儞僌偱婃挘偭偰壓偝偄両 徻偟偔偼丄惀旕斣慻傪偛棗偔偩偝偄丅 傛傒偆傝僥儗價丂4寧6擔乮擔乯丂偁偝6帪15暘乣30暘偱偡丅 |
||